| 用船契約は、大別すれば定期用船契約、裸用船契約、航海用船契約の3つに分かれるが、元請として特に重要なのは、・・・・・・・・用船契約で、この場合、用船契約の当事者は・・・・・・者と・・・・・荷主である。 運送上の船主責任や免責、などは国際条約の Hague Visby Rule を批准し、各国の国際海上物品運送法(COGSA: Carriage of Goods by Sea Act)のもと・・・・・・に適用されるが、これは・・・・・用船契約には適用されないことになっている。概略すると、用船者たる単なる荷主は用船契約上で物を言うことができ、・・・・・・・所持人である荷主は・・・・・・・・・発行人責任者に・・・・・・・・上の契約のもとに話ができるということです。 Hague Visby Rule では・・・・・に不利益な・・・・・は無効とする。ただし、・・・・・人に不利益な・・・・・をすることは妨げない。と規定しているが、この・・・・・規定は先に記したのと同様、・・・・・用船契約に適用されないとされている。 日本においては海上運送契約になんらかの特約を規定をプラスして用船契約に準用されることも多く。荷主が・・・・・所持人であって、相手が純粋なる・・・・・者である場合には用船契約上で話をできるが、そうでない場合も多々あるので、荷主は自己の立場が・・・・契約上にあるか、・・・・契約上のあるかをよく確かめておかねばならない。 元請はこれら契約条項がどのように結ばれているかをおおまかに把握し、疑問は適宜関係人に問い合わせて払拭しておかなければ、大恥で済まされぬ結果を生む事がある。 ・・・・も・・・・・も同じ・・・契約であって、実際はその主要な部分の構成に相違はないと考えられる。それらは、 ①船主名 ②用船者名 ③船名 ④積載量 ⑤From to ⑥運賃 ⑦・・・・・条件 ⑧・・・・料 ⑨・・・・料 ⑩・・・・戻し ⑪港・・・・・・条項 ⑫積揚地代理店指定 ⑬・・・・・・条項 ⑭用船者責任 ⑮ストライキ条項 ⑯戦争危険約款 ⑰共同海損 ⑱衝突約款 ⑲離・・・・回約款 ⑳契約違反賠償条項 その他 等様々な条項により完成される。この中でも、・・・・ の表面に書いてあることはよくご存知だと思いますが、さて裏面に小さな文字で書かれている約款を読まれた方はどれくらいおられるでしょうか? COGSA または ・・・・・・・・・・ にのっとって、こと細かく書かれています。非常に大切なことが書いていますから元請におられる方は一度くらい読んでおきましょう。 |
||
| 元請の憂鬱と大罪 Ⅱ | ||
上記の内容をフルスペックでご覧になりたい方は以下にてお願いします↓ |
||
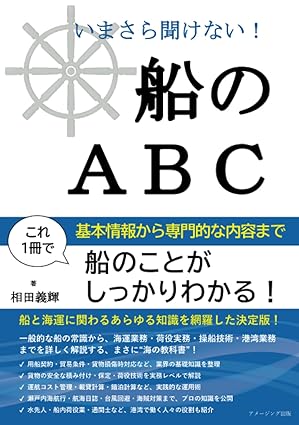 |
||